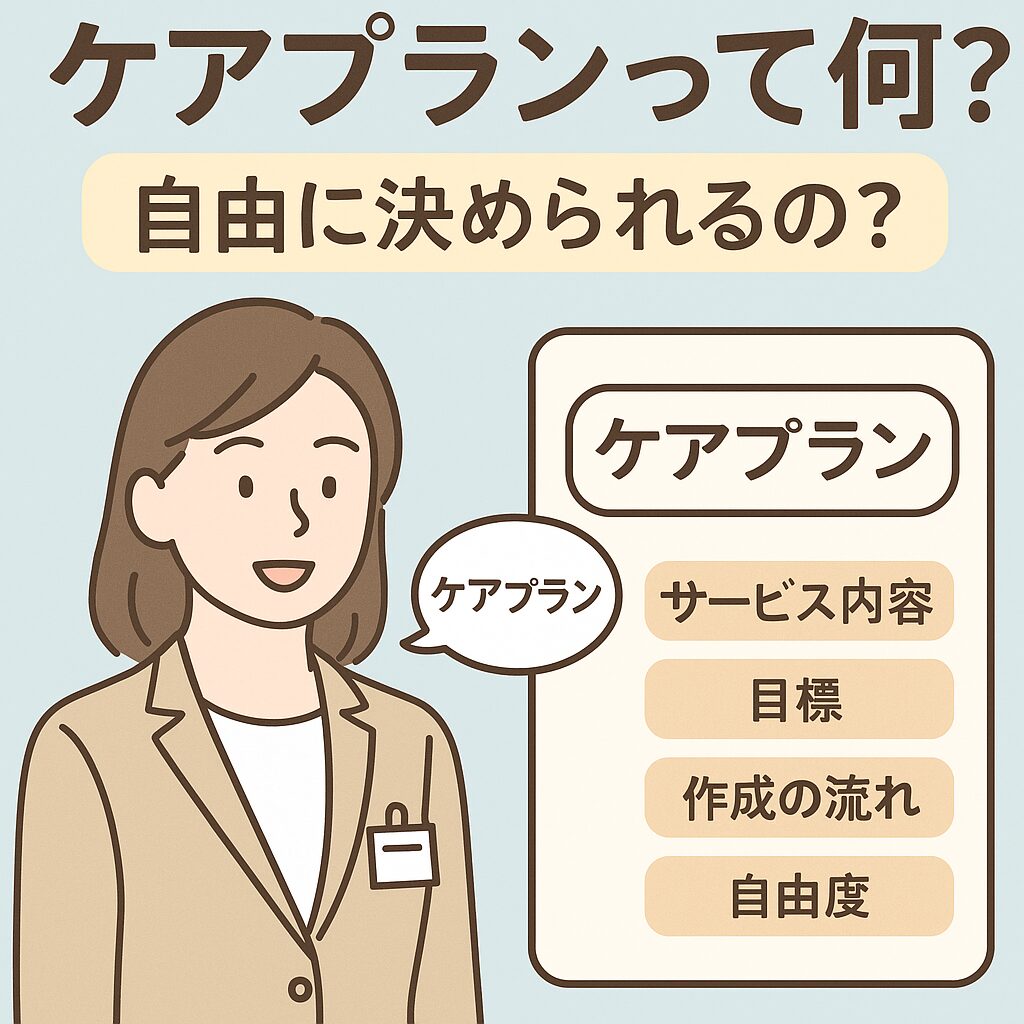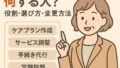ケアマネジャーが初めて家に来たとき、こう言われたことはありませんか?
「では、ケアプランを作りますね」と。
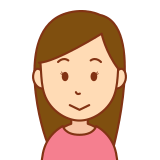
ケアプランって何?
それって全部ケアマネさんが勝手に決めちゃうの?って思いませんでしたか?
中には「ケアプラン」の意味を、丁寧に説明してくださるケアマネさんもいるとは思いますが
この記事では、ケアプランの意味・作成の流れ・どこまで自由に決められるかを、はじめてでもわかりやすくご紹介したいと思っています。
ケアプランとは?簡単にいうと・・

ケアプラン=「介護サービスの利用設計書」です。
たとえば…
- 週に2回ヘルパーが来る
- 週1回デイサービスに行く
- 月に1度、福祉用具の点検を受ける
このような「いつ・何を・どのくらい使うか」を具体的にまとめたものが、ケアプランです。
ケアプランって自分にも作れるの?
基本的には担当のケアマネジャーが作成します。
ただし、本人や家族が「こうしたい」と伝えた希望をもとに作るため、一方的に決められることはありません。
※実は「セルフケアプラン(自分で作る)」も法律上は可能ですが、ほとんどの人はケアマネに作ってもらっています。
ケアプランの中身とは?
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 本人の課題 | 一人での入浴が不安/転倒のリスクあり |
| 目標 | 週に1回のデイ利用で交流を増やす |
| サービス内容 | 訪問介護(掃除・調理)、福祉用具レンタル(手すり)など |
| 事業所名と回数 | ○○訪問介護:週2回、△△デイ:週1回 |
この表のように、ケアプランには生活のさまざまな事が書かれています。
ケアプランはどのくらい自由に決められる?
かなり自由です!が、注意点もあります。
- 予算の範囲内である必要がある(要介護1なら約17万円分/月)
- 提供できるサービスが地域で異なる(地方では選択肢が少ないことも)
- ケアマネの提案に納得できない場合は変更も可
たとえば、
「週2のデイは本人が嫌がっている」
「家族が介護するからサービスは少なめにしたい」
など、希望はちゃんと反映されるべきです。
ケアプラン作成の流れ
【ケアプラン作成の流れ】
1. ケアマネが自宅訪問
2. 本人・家族の希望や困りごとをヒアリング
3. 状況に合ったサービスの提案
4. 内容に同意 → ケアプラン完成
5. サービス事業所と契約 → 利用開始
このように「包括センター」に行ってから、実際に動き出せるまで時間がかかります。
「ちょっと変だな?」
と異変を感じたら、早め早めに対応していく事が、本人にも家族にも最善だといえます。
よくある質問
Q.「ケアマネが勝手にデイサービスを決めた」と聞いたけど?
→ 提案はしますが、同意なく始めることはできません。遠慮せず相談を。
Q. 自宅での介護が中心でも、ケアプランって必要?
→ はい。訪問や福祉用具だけでも計画書が必要になります。
Q. 途中でプランは変えられる?
→ もちろんOK!状態や気持ちに合わせて、いつでも見直せます。
ケアプラン作成では、つい「プロが言うなら…」と全部お任せしてしまいがちです。
でも本当は、
「それはちょっと違う気がします」
「他の選択肢もありますか?」
と遠慮なく伝えることが大切です。
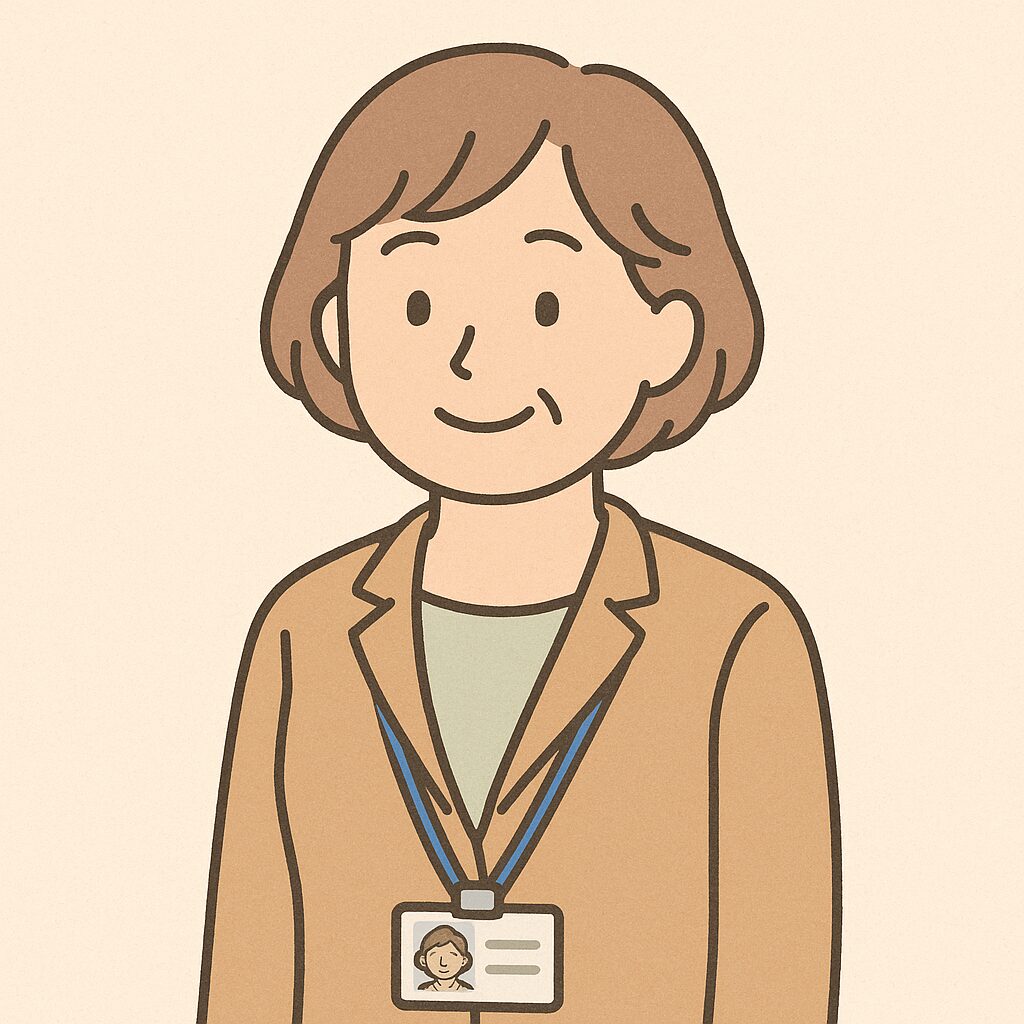
ケアマネジャーはあくまで「ご本人とご家族の希望に沿ったプランを一緒に作る」パートナーです。
不安や疑問があるときは、一人で抱え込まずに相談しましょう。必要であれば、ケアマネの変更や再検討も可能です。
介護は“チーム戦”です。あなたの声が、より良い介護生活をつくる大切な一歩になります。
ケアプランは「生活の地図」
ケアプランは、介護生活を迷わず進めるための地図のような存在。
ケアマネに任せきりにせず、家族も一緒に「どう暮らしていきたいか」を話すことで、もっと納得のいく介護生活が始まります。
ある家族のケアプランの例
実際に、私の知人のお母さまが要介護1と認定され、ケアマネさんと話し合って決めたプランがあります。
最初は「デイサービスは嫌」とお母さまが拒否していたため、無理に入れず、まずは週に2回のヘルパー訪問からスタートです。
「掃除と洗濯を少し手伝ってくれるだけで助かる」
と話されていて、本人の気持ちを優先したプランにしたそうです。
数ヶ月後、訪問してくれるヘルパーさんに少しずつ心を開き、
「この人とならデイサービスにも行ってみようかな」
と言ってくれるようになったとのこと。
『最初から詰め込みすぎず、本人のペースに合わせたプランが結果的にうまくいった』
という好例でした。
最後に
歳を重ねると「新しい環境」や「新しい人付き合い」は億劫になって当たり前です。
しかし、介護する家族にとっては
『できるだけ安心な環境で過ごしてもらいたい』
と考えると、意見に大きな差が出てきてしまいがちです。
また、ケアマネさんの意見は、数多くの人を見てきたからこその部分もあるで、家族には受け入れ難いと感じることもあるでしょう。
そういう時は、ぜひ妥協せず話し合ってみてください。
この世にたった1人の母親であり、父親の余生を楽しく過ごしてもらうためにも、ここはしっかり納得できる道を見つけてください。
0心から応援しています。